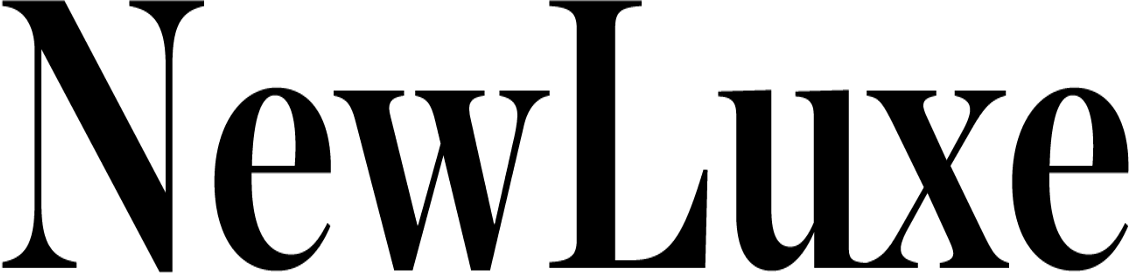映画批評:戦争、愛、記憶を探る「マザーリングサンデー」

This image released by Sony Pictures Classics shows Odessa Young, left, and Josh O’Connor in a scene from "Mothering Sunday." (Jamie D. Ramsay/Sony Pictures Classics via AP)
|
|
|
歴史は事実である。歴史は年代順だ。歴史は直線的。しかし、記憶は?記憶はそのどれでもない。
記憶は選択的であり、混乱し、さまざまな方向へ移動する。そして、エヴァ・フソンは、愛と喪失に関する瞑想を、その長い人生を通して反響する衝撃的な日の女性の記憶に基づいて、気だるいながらも印象的で視覚的に楽しい「マザーリング・サンデー」に表現している。
最初は、戦後の20年代、40年代、80年代と、時代の跳躍が耳障りに感じられるかもしれない。しかし、すぐにフッソンは、これが記憶の仕組みであることを理解させ、このリズムが意味をなすようになる。
しかし、グレアム・スウィフトの2016年の小説を基に、アリス・バーチが巧みに脚色した『マザーリング・サンデー』は、記憶だけについての作品ではない。戦争、すなわち第一次世界大戦と、それが息子の世代をまるごと失った、ここにあるイギリスの村のような無数の村にもたらした荒廃についても描かれているのだ。
また、愛やセックス、そして階級についても描かれている。この2人の恋人を隔てる消えない線は、新鮮な顔立ちで思慮深いオデッサ・ヤングとジョシュ・オコナーが真の親密さで演じているが、『The Crown』での抑圧されたチャールズ皇太子とはまったくかけ離れている。この緊張感のある親密さ、そして臆面もないヌードは、フランス人らしい率直な性向で、堅苦しい英国上流階級を描いたユソン監督に感謝したい。
しかし、「Mothering Sunday」は、子供を失った両親の顔に深く刻まれた悲しみを描いた作品である。これほど悲しく、絶望的なコリン・ファースの姿は見たことがない。絶望的なまでに偽りのない明るさで、悲しみを振り払おうとする父親を演じる。このような努力は、オリヴィア・コールマンが演じる妻のクラリーには何の役にも立たない。かつては快活な女性だったが、塹壕で2人の息子を亡くして以来、苦々しい殻に閉じこもってしまったのだ。クラリーのセリフは少ないが、すぐに忘れることのできない抑制された苦悩でそれを口にする。
このカップルが十分なドリームキャスティングでないなら、主人公ジェーン・フェアチャイルドの半世紀後の自分を演じるのは、ほかならぬグレンダ・ジャクソンである。しかし、それについてはまた今度。
舞台の大半は1924年、3家族が生涯の友となる美しい村の春の日である。ニヴン家のメイド、ジェーン(ヤング)は、雇い主(ファースとコルマン)から休みの日を提示され、朝食を出しているところだ。その日はマザリング・デイ、つまり母の日なのだが、ジェーンは孤児なのだ。そこで彼女は、秘密の恋人である法学部の学生ポール・シェリンガムと密会するため、自転車で出かける。
もちろん、二人の恋は禁じ手だ。ジェーンは、長年の恋人と第三家族の娘の婚約に立ち会わなければならなかった(彼らに夕食をご馳走しながら、である)。結婚式が近づき、この日曜日、家族たちは川辺に集まって祝おうとする。しかしその前に、ポールはジェーンと情熱的な愛を交わし、彼女を残して広い実家を裸で探索する。
しかし、これは幸せな昼食会ではなく、間もなく起こる衝撃的な出来事のためでもあった。ゴッドフリー(ファース)が陽気に乾杯しようとすると、コルマン演じるクラリーが暴発し、皆が感じる永遠の痛みを痛烈に表現しているのだ。
この1924年のシーンは、1940年代の広範なシーンと切り替わり、年老いたジェーン(やはりヤング)は、執筆活動をしながら書店で働くようになる。そこで彼女は、新しい恋人ドナルド(ソペ・ディリス)と出会い、哲学をめぐって心を通わせていく。サンディ・パウエルの素晴らしい衣装は、丹念に作られた20年代のドレスから、ジェーンがスマートなベレー帽を被って着る40年代のシックなベルテッド・コートへと変化していく。
ジェーンがどのような作家になっていくのか、私たちにはよくわからない。ナレーションがないので、ジェーンが夢のような記憶の中で発した言葉がちらほらと聞こえてくるだけだ。
このギャップは、最終章でジャクソンがほんの少し登場することでより顕著になる。老いたジェーンは大きな文学賞を受賞したところだった。彼女は外で待つ報道陣に向かって、「私はすべての賞を受賞しました」と疲れ切った様子で言う。”一つ残らず “と。
ジェーンがどんな素晴らしい作家になったのか、もっと知りたいものです。二人のジェーンが数十年の時を越えて目を合わせ、素敵な視覚的つながりを得ることができました。彼らは何を考えているのだろう?
この映画の多くがそうであるように、それは素晴らしいものであるが、ほんの少し手が届かないところにある。